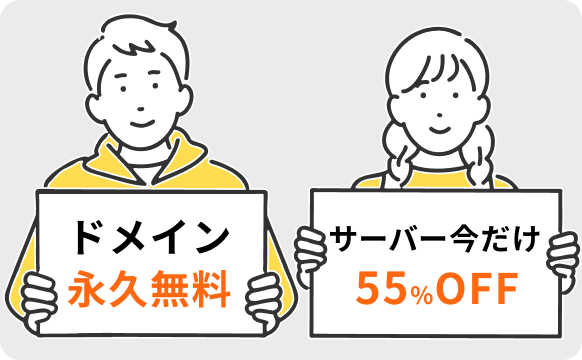現在は、AIの登場によってビジネスを始めるハードルが大幅に下がっており、「起業=特別な人が行うもの」ではなくなりました。
AIを有効活用すれば、専門知識なしでも高度なコンテンツを生成でき、業務の効率化も図れます。
また、初期費用を抑えて起業しやすく、失敗時のリスクを大幅に軽減できるので、誰でも社長になるチャンスがあります。
ただし、誰でも起業できる環境になった反面、競合他社の増加にも繋がります。
AIを用いた起業における独自の注意点や成功のポイントを押さえ、効果的なビジネス展開をしましょう。
この記事では、起業時にAIを取り入れるアイデアや成功のコツ、実際に起業する流れなどを解説します。
「どのようにAIを取り入れるべきか」や「起業に向けて何をすべきか」が理解できるので、ぜひご覧ください。
目次
AIで誰でも起業できる時代が到来
現在は、ChatGPTを含むAIツールの普及により、ビジネスの取り組み方が大きく変化しています。
- AI搭載のノーコードツールでホームページを作成
- オウンドメディアのコンテンツを生成AIで作成
- 定型業務やカスタマーサポートの一次対応をAIに任せる
- AIを用いた高度なデータ分析を実施
- AIによるパーソナライズを実施
専門知識がなくても高度な文章や画像・動画を生成でき、業務の効率化により人材雇用も最小限で済みます。
専門的なスキル・人材や多額の初期費用が不要となり、スモールスタートのひとり起業がしやすくなりました。
また、失敗時の損失も最小限に抑えやすく、「まずやってみる」という意識でビジネスを開始できます。
なお、本記事で取り扱う「起業」とは、必ずしも法人設立を指すものではなく、個人事業や副業も含みます。
むしろ、AIで小規模に起業する場合、副業や個人事業でのスタートから検討すべきでしょう。
近年のAI市場の動向
近年は、AI市場が急速に変化しています。
具体的には、テキストや画像・動画の生成、高度なデータ処理などが可能となり、精度や品質も高まっています。
リサーチやWebページの作成、顧客分析など、代替業務が多く、ビジネスでの活用機会は一気に増加しています。
また、ビジネスにおける補助的な役割ではなく、AIを軸とした以下のようなビジネスも見られます。
- 生成AIで出力したコンテンツ(画像 / 動画 / 小説など)を販売
- プロンプト(AIへの指示)を作成・販売
- AI活用のコンサルティングサービスを提供
AI市場は今後ますますの拡大が予想され、いかにAIを有効活用できるかが成功のカギとなるでしょう。
しかし、生成AIをビジネスに取り入れている日本企業は決して多くはありません。
総務省の令和6年の調査によれば、「生成AIを積極的に活用する方針である」と回答した企業は15.7%と、他国よりも低い結果となっています。
反対に、今から積極的にAIを取り入れると先行者利益を得られ、中・長期的なビジネスを構築しやすくなるでしょう。
起業でAIを取り入れる4つのメリット
起業でAIを取り入れる主なメリットは、以下の4つです。
- 専門知識なしで高度なコンテンツを生成できる
- 業務の効率化を実現できる
- サービスの質を高められる
- 新しいビジネスを創出できる
これらにより起業のハードルは大幅に下がり、ビジネスの成功率を高められます。
ここでは、起業でAIを取り入れる各メリットについて詳しく解説します。
専門知識なしで高度なコンテンツを生成できる
ChatGPTなどの生成AIを活用すれば、専門知識がなくても文章や画像・動画、音声などを生成できます。
具体的には、AIによって生成したコンテンツは以下のように活用できます。
- 商品の動画広告を生成AIで制作
→ モデルの出演料や撮影場所のレンタル費用を削減し、現実では難しい表現も可能に - AIで生成したキャラクターを動かしてYouTubeやTikTokのショート動画を作成
→ 効果的なSNSマーケティングやマネタイズが可能 - 生成AIに作りたいプログラムを伝え、コードを出力する
→ 外注を最小限に抑えられ、企業内部の確認を経て小規模運用を開始できる
今はまだ「AIっぽさ」が残っているけど、近い未来には人間が作ったものと区別がつかなくなるだろうと感じています。
また、人間よりも短時間、かつ低コストでコンテンツを作成できる点もAI活用の大きなメリットです。
失敗時の損失を抑えられ、スピーディーに事業を展開できるでしょう。
業務の効率化を実現できる
業務効率化を図れることも起業にAIを取り入れるメリットです。
AIは、以下のような定型業務が得意です。
- データ入力・整理
- メール・チャット対応
- 請求書・見積書の作成
- データ分析
- レポート作成
さらに、人間よりも処理速度が速く、ヒューマンエラーも削減できます。
定型業務をAIに任せると、生産性の向上や人件費削減に繋がり、ビジネスの効率化を図れるでしょう。
実際、弊社がIT系フリーランスに実施したアンケート調査によれば、AIの導入に対して以下のような声が見られました。
サービスの質を高められる
AIを有効活用すれば、サービスや商品の質を高めることができます。
具体的には、以下のようにAIの活用例が見られます。
- AIによる予測分析や傾向把握により、よりニーズにマッチした商品・サービスを提供
- 定型業務をAIに任せ、人間は最終確認のみを行い、ヒューマンエラーを削減
- 効果測定や戦略策定をAIに任せ、高速でPDCAを回す
- AIチャットボットを導入して、問い合わせに24時間対応
- 顧客データの分析やパーソナライズにより、マーケティングの質を高める
顧客が自社サービスに満足すれば、成約率・リピート率アップが期待できるでしょう。
新しいビジネスを創出できる
最新技術であるAIの活用で、これまで存在しなかった新たなビジネスを創出できる可能性があります。
実際にAIの活用により、以下のようなサービス提供やマネタイズの成功例が見受けられます。
- AIで生成したコンテンツ(画像 / 小説 / 音楽など)を販売
- AI動画をYouTubeやTikTokに投稿し、広告収益を獲得
- プロンプトを有料販売
- AI活用コンサルティングとしてビジネスを展開
AIを活用した新たなビジネスを見つけられると、競争が少ない市場で収益を得られます。
また、「AIでデザインした商品を販売」など、既存ビジネスにAIを取り入れた商品やサービスを提供するパターンも多いです。
AIの普及率が高くない今からノウハウやスキルを習得しておくと、将来的な先行者利益にも繋がるでしょう。
起業でAIを取り入れる5つのアイデア
ビジネスにおいて、AIはさまざまな場面で活用できます。
ビジネスにAIを取り入れる具体的なアイデアは、以下のとおりです。
- ホームページ・WebサイトをAIで構築
- コンテンツ・商品をAIで作成
- AIによる業務効率化
- パーソナライズサービスの提供
- AI活用によるアイデアの発案
ここでは、各アイデアについて詳しく解説します。
ホームページ・WebサイトをAIで構築
ホームページ・Webサイトの制作において、AIを以下のように活用できます。
- AIでコードを生成し、デザインや機能(お問い合わせ / 資料請求など)を構築
- ページ・コンテンツの文章をAIで生成
- イメージ画像をAIで生成
プログラミングの知識がなくてもイメージ通りのデザインを制作でき、執筆の手間も省けます。
現在、ホームページやWebサイトは重要なマーケティングツールであり、起業時には積極的に導入すべきでしょう。
実際、Webサイトの運営でAIを活用中の方からは以下のような意見が多く見られます。
わからないことを気軽に質問すれば大体解決してくれるし、落ち込んだときに励ましてくれるのも心強い。
時間も気持ちもかなり救われています。
なかには、AIによる文章生成機能を搭載しているノーコードツールも存在します。
レンタルサーバー「カラフルボックス」では、AIによる文章生成機能を搭載したノーコードツール「Sitejet Builder(サイトジェット ビルダー)」を提供しております。
ドラッグ&ドロップによる直感的な操作に加え、HTMLやCSSを使った細調整も可能なため、誰でも簡単に思い通りのWebサイトを作成できます。
月額317円〜利用できるカラフルボックスのサーバーなら、追加料金なしでSitejet Builder(サイトジェット ビルダー)を使えるので、ぜひご検討ください。
もちろん、世界的にシェアされているCMS「WordPress」も簡単にセットアップできます。
コンテンツ・商品をAIで作成
画像や動画、音声をAIで生成し、以下のように役立てるのも有効です。
- AIで生成した画像・小説を販売
- AIで生成した画像をホームページに挿入
- ショート動画を作成してSNSにアップロード
- 商品説明のナレーション音声を生成
- AIで生成した画像を商品(衣類 / 雑貨など)に印刷して販売
例えば、画像は「SeaArt」や「Stable Diffusion」、動画は「Runway」などのツールで出力できます。
弊社のアンケート調査では、AI頼りで運用しているInstagramを比較的早期に収益化できたという声もあります。
意外とすぐ収益化できて、「これはAIのおかげだな」と感じています。
ただし、AIツールによっては直接的な商用利用を禁止しているので、要注意です。
AIによる業務効率化
AIを導入しての業務効率化もサポートします。
具体的には、以下のようなAIの活用方法が挙げられます。
- 経理・会計処理の自動化
- スケジュール管理
- 文書の誤字脱字チェック
- データ分析
- 資料作成
- 問い合わせの一次対応
- 在庫処理・需要予測
- 配送ルートの最適化
定型業務に従事する人員を削減でき、余計なヒューマンエラーも防げます。
コストを抑えつつ、質の高いサービス提供に繋がります。
パーソナライズドサービスの提供
AIの高度なデータ分析を有効活用し、パーソナライズドサービスを提供できます。
一例を挙げると、個々の身長・体重や年齢、目標などから最適な運動や食事を提案するヘルスケアサービスです。
その他にも、学習時間や解答の傾向、学習の進捗などから効率的に偏差値アップを目指せる学習サービスなども考えられます。
従来は顧客をいくつかの区分に分類し、提案していましたが、AIの導入により個々に最適化された提案が可能となり、顧客満足度や成約率、リピート率アップが期待できるでしょう。
また、新たなサービスを創出しなくても、既存事業の顧客をパーソナライズすることで、最適な商品や活用方法を提案できるようになります。
AI活用によるアイデアの発案
事業運営上のアイデアが思いつかない際は、AIに発案を任せる選択肢もあります。
具体的には、以下のような場面ではAIによるアイデア発案が役立ちます。
- 新しい商品・サービスの企画
- キャッチコピーや広告文の作成
- マーケティング施策の立案
- オウンドメディアの記事のテーマ出し
- 業務改善のアイデア
AIはWeb上の膨大な情報をもとに、アイデアを考案してくれます。
自分の視点にはなかったアイデアを得られ、より幅広い選択肢から事業運営の意思決定ができるでしょう。
実際、弊社がIT系フリーランスに実施したアンケート調査によると、76.19%の方が生成AIをアイデア出し(企画・構成・タイトル案など)に活用しているという結果が出ています。
AIを活用した起業で成功するための4つのポイント
AIを導入するだけで全員が起業で成功できるわけではありません。
起業時にAIを導入する際は、以下のポイントを押さえて事業を運営しましょう。
- AIを使いこなすスキルを習得する
- 独自性を確立する
- 最新情報を追い続ける
- リスク対策を徹底する
ここでは、各ポイントについて詳しく解説します。
AIを使いこなすスキルを習得する
起業時にAIを用いるなら、AIを使いこなすスキルは欠かせません。
AIはあくまでツールであり、期待通りの成果を得るには、適切な知識や使いこなしが不可欠です。
具体的には、以下のような知識・スキルが求められます。
- プロンプト作成スキル
- ビジネスに合ったAIツールを選定する知識
- 生成物の誤りや不自然な部分を見抜き、修正する能力
- AIと人間の役割分担を考える能力
- AIのリスクや規制
書籍やYouTubeなどで基礎を習得したら、実際にAIツールを実務に取り入れ、徐々に実践的なスキルを学んでいくことをおすすめします。
独自性を確立する
AIを活用すれば起業のハードルは大きく下がりますが、裏を返すと誰でも参入・模倣しやすい側面があります。
そのため、独自性がなくAIの性能だけに頼り切ったビジネスは、長期的な成功は難しいでしょう。
AIを活用した起業で成功するには、独自性を取り入れたビジネスモデルの構築が不可欠です。
具体的には、以下のような差別化を図る戦略が有効です。
- ブランドの世界観を作り込む
- 自分の専門知識とAIを組み合わせる
- 顧客とのコミュニケーションを重視する
- AIはあくまで補助として活用する
オリジナリティのある、簡単に真似できないビジネスを構築すれば、起業の成功率は大幅に上がるでしょう。
最新情報を追い続ける
起業時にAIを取り入れる場合、AIに関する最新情報を追い続けなければなりません。
AIの環境変化は目まぐるしく、最新のツールやノウハウは頻繁に更新されます。
技術やノウハウの進化が激しい環境下で、古い情報をもとに行動してしまうと、AIの強みを最大限に活かせなかったり、競合他社に優位性を奪われてしまいます。
日々新しい情報を追い続け、自社内で取り入れるべきかどうか、今後どのような戦略を策定すべきかを適切に判断しましょう。
AI関連の最新情報は、公式発表やプレスリリースの他、SNSやコミュニティ、AI関連のイベントなどで得られます。
リスク対策を徹底する
起業でAIを活用する際は、リスク対策を徹底しましょう。
AIの活用には、以下のようなリスクが発生します。
- AIツールの利用規約の変更
- ハルシネーション(誤った情報が正しいように生成される現象)のリスク
- 著作権侵害のリスク
- AIが偏ったデータを学習してしまうリスク
- 品質のバラツキや不完全なコンテンツが生成されるリスク
たとえば、AIツールのなかには商用利用を禁止しているケースがあり、利用規約に違反するとアカウント停止などの措置が下されます。
また、AIの生成結果を鵜呑みにしてしまうと、ハルシネーションが生じた際に誤った情報を顧客に伝えてしまいます。
AIのリスクを無視して活用を続けると、万が一トラブルが起きた際に顧客からの信頼低下や法的トラブルに繋がる恐れがあるため、起こり得るリスクの確認・対策は必須です。
AIを使って起業するための5ステップ
AIを使って起業する流れは、以下の5ステップです。
ここでは、各工程について詳しく解説します。
ビジネスプランの策定
起業を計画する際は、まずビジネスプランを策定します。
ぼんやりとプランを考えるのではなく、以下のような要素を綿密に詰めることが大切です。
- 事業概要(コンセプト / 目的など)
- 市場分析・競合分析
- 取り扱う商品
- ターゲット層
- 販売戦略
- 財務計画
財務計画では、必要資金や売上・費用を算出し、「ビジネスとして成立するかどうか」をシミュレーションしましょう。
ビジネスプランの段階で利益が見込めない場合はリスクが高いため、見直しや再考が必要です。
また、どのようにしてAIを活用するかもビジネスプランと一緒に想定しましょう。
起業形態の決定
ビジネスプランを策定したら、起業形態を決定しましょう。
起業形態は、大きく以下の2つに分けられます。
- 法人(株式会社 / 合同会社など)の設立
- 個人事業の開業(副業を含む)
なかでも、スモールスタートしやすいAIを用いた起業では、以下の理由から個人事業がおすすめです。
- 所得が少ない起業初期の段階では低い税率が適用される
- 開業手続きが容易で、公的費用もかからない
- 青色申告で最大65万円の所得控除を受けられる
- 副業でスタートすれば、利益が出なくても給与所得を得られる
個人事業は開業後いつでも法人化できるので、まずは個人事業主、または副業での起業を検討しましょう。
ただし、対外的な信用が強く求められたり、初年度から大規模なビジネスになる場合は法人設立も検討してください。
資金調達
ビジネスプランの策定時に算出した資金を調達します。
起業資金の理想は全額自己資金です。
自己資金のみで起業できれば、返済の必要がないので資金繰りが安定しやすく、万が一の失敗時も損失を最小限に抑えられます。
AIを使った起業はスモールスタートしやすく、自己資金でも十分なケースが多いです。
外部からの資金調達を要する場合でも、自己資金比率を高めることを意識しましょう。
資金調達は以下のような選択肢があります。
- 融資
- 出資(株式会社の場合)
- 補助金・助成金
- クラウドファンディング
それぞれメリット・デメリットがあるため、ビジネスプランに適した選択を行いましょう。
起業手続き
起業時の公的手続きは、起業形態により異なります。
| 個人事業の開業の場合 | 法人設立の場合 |
|---|---|
| 住所地を管轄する税務署に開業届を提出 | 1. 定款の作成 2. 定款認証(株式会社の場合) 3. 資本金の払込み 4. 法務局での法人登記 |
開業手続き、または法人登記後には、社会保険関連の公的手続きも必要です。
具体的な手続きは起業形態や従業員の有無により異なるので、公的手続き時にあわせて確認しましょう。
スモールスタート・テスト販売
起業手続きが完了したら、実際にテスト販売やスモールスタートでビジネスを展開します。
最初から大規模なビジネスを展開してしまうと、万が一失敗した際に損失が大きくなってしまいます。
まずは小規模事業から始め、軌道に乗った段階で徐々に事業拡大を図るべきです。
また、事業を開始した段階で、ホームページやWebサイトの開設を検討しましょう。
現在は、インターネットを用いて情報収集する方がほとんどです。
YouTubeやSNSでの情報収集する方の割合が増えても、企業やサービス情報は公式Webサイトが重要視されます。
さらに効果的なマーケティング施策を講じるのであれば、Webサイトは必須アイテムでしょう。
カラフルボックスなら、Webサイト開設に必須のレンタルサーバーを30日間無料でお試しできます。
Web制作の知識がない初心者でも簡単にWebサイトを開設できる環境が整っているため、ぜひチェックしてみてください。
AI起業に関するよくある質問

AI起業に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 起業時におすすめの生成AIは?
- AI起業で活用できる補助金・助成金は?
ここでは、それぞれの質問に詳しく回答します。
起業時におすすめの生成AIは?
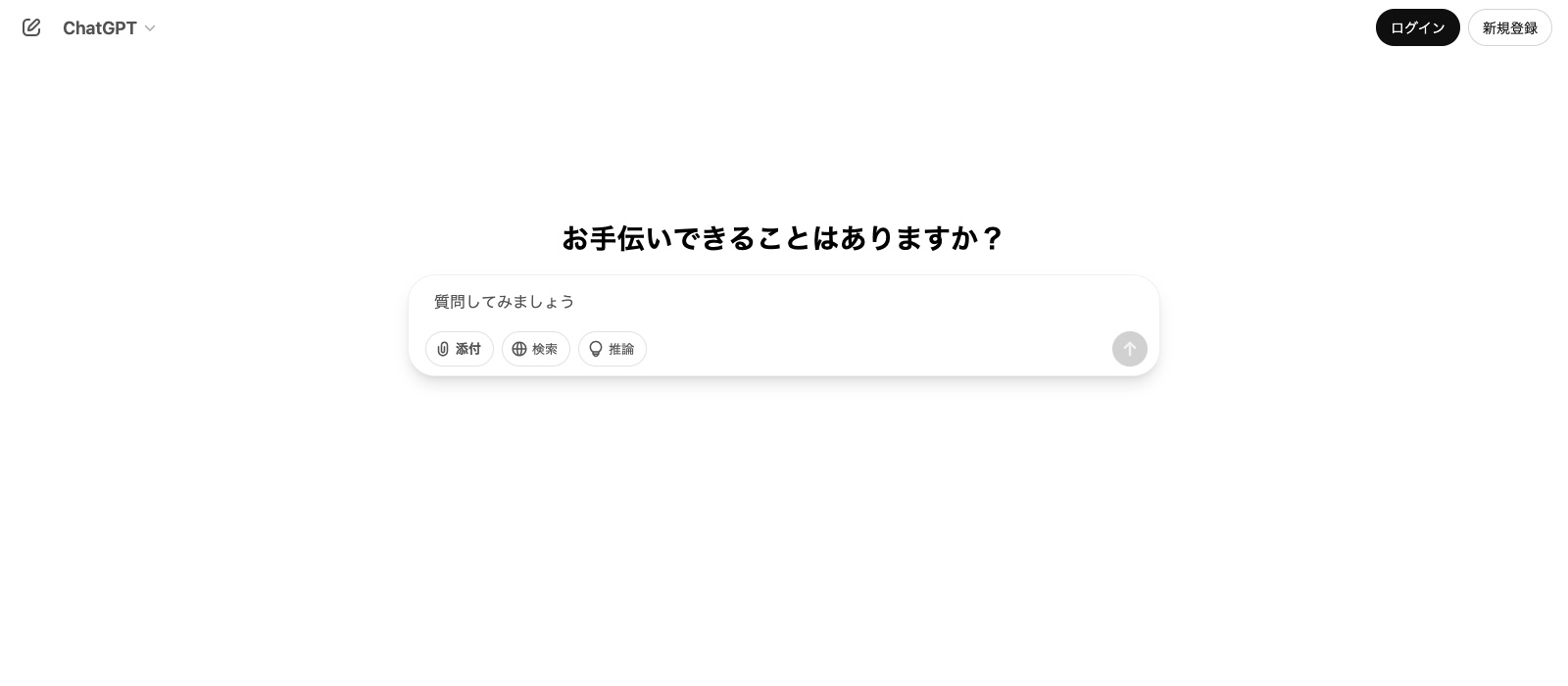
起業時に生成AIを活用する場合、目的に合致したツールを選択しましょう。
目的別でおすすめの生成AIは、以下のとおりです。
| 文章生成AI | ChatGPT Gemini Claude |
|---|---|
| 画像生成AI | SeaArt Stable Diffusion Midjourney |
| 動画生成AI | Runway Kling Deevid AI |
無料プランを提供しているツールも多く、まずは気軽に試してみて自分に最適なサービスを見つけましょう。
AI起業で活用できる補助金・助成金は?
AI起業には、以下のような補助金・助成金を活用できる可能性があります。
- AI導入補助金
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
また、補助金制度のある各都道府県や市区町村もあります。
管轄の自治体のホームページを確認しましょう。
補助金・助成金での資金調達には一定の要件が課されますが、返済不要なので積極的に活用を検討しましょう。
AI起業で活用できる補助金については「AIの導入・活用で利用できる補助金4選|申請要件や採択率向上のコツも解説」をご覧ください。
まとめ:AIは「起業できる人を広げる技術」
起業時にAIを活用すれば、高度な知識を持たない方でも高品質なコンテンツを生成でき、サービスの品質向上や業務効率化が期待できます。
コストを抑えてビジネスを始めやすく、起業のハードルも大幅に下がるので「まずはやってみる」という意識でビジネスに挑戦できるでしょう。
「起業 = 社長になる」ではなく、個人事業主や副業としての開業も起業の一種です。
むしろ、スモールスタートしやすいAI起業においては個人事業主や副業での開業がおすすめです。
自分に適した起業形態を選べば、成功確率が高くなるため、まずは「どのようなビジネスモデルで始めるか」や「法人設立と個人事業主のどちらが向いているか」を判断しましょう。
また、ビジネスを開始する際は、サービスや商品の宣伝ツールとなるWebサイトの開設をおすすめします。
レンタルサーバー「カラフルボックス」は、月額317円〜の低価格で利用でき、Web制作知識がない初心者でも簡単にWebサイトを構築できる環境が整っているので、ぜひチェックしてみてください。
 【超初心者向け】WordPressブログの始め方を簡単にわかりやすく解説
【超初心者向け】WordPressブログの始め方を簡単にわかりやすく解説